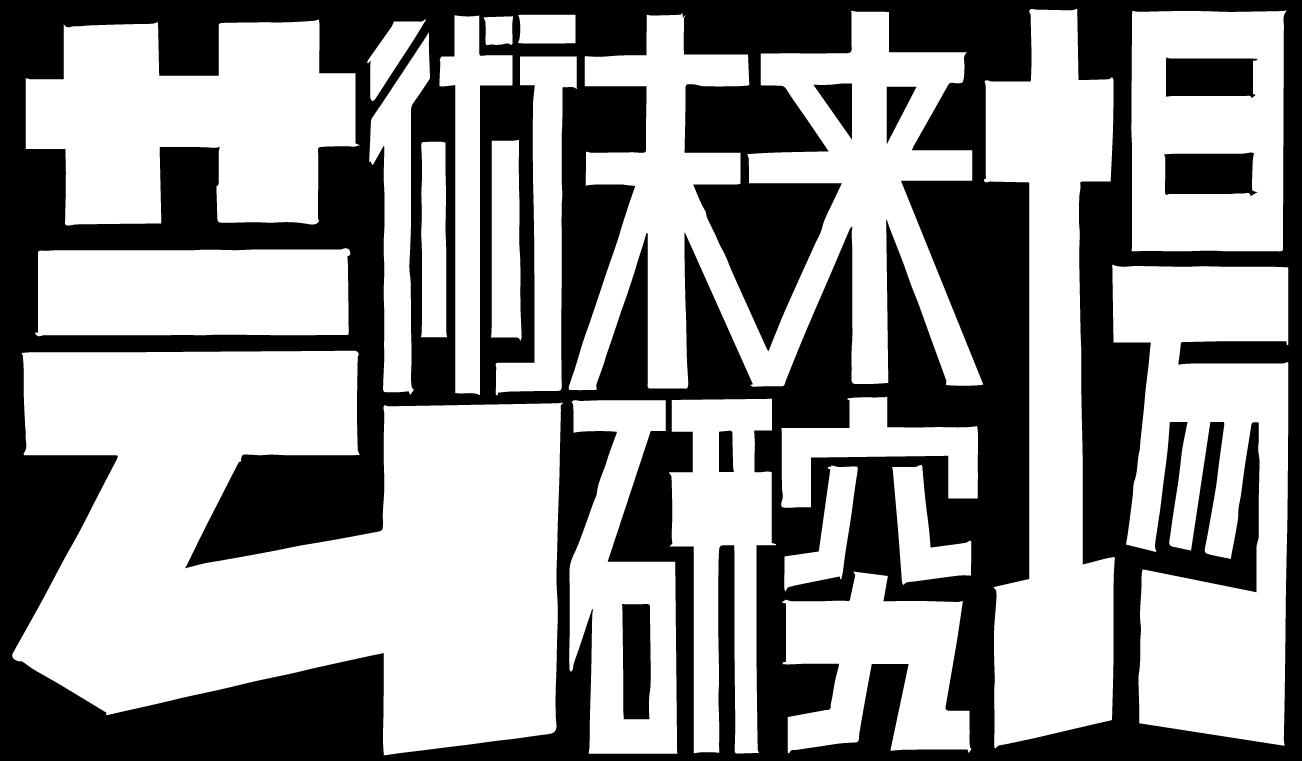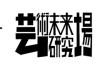-
特別プロジェクト
Shrine to Earth
大学美術館
スペンサー・チャンの実践は、インターネット環境、オープンソースのインスタレーション、そしてデジタル的存在の別様のあり方を提示するコンピューティングを取り込んだ彫刻作品を含んでいる。
チャンの《Computing Shrines(コンピューティングの社)》シリーズは、発見されたオブジェクトに彫刻的な拡張を施すことで形成される、場所特有の共同的インターフェイスである。イサム・ノグチの実現しなかった遊具デザインに着想を得て、遊びや風変わりな発想を通じて地域的なつながりを育む。
それぞれの「社」は、過去と未来の来訪者の交流を記録するウェブ体験へのポータルとして機能する。《Shrine to Earth》では、観客が自ら見つけた石の写真を投稿し、それが石を積み上げるミニゲーム内で使用されるよう促される。観客は過去の投稿をクリックして、石の情報や追加された時期を知ることができる。これらのデジタル・アーカイブへのアクセスは、対応する「社」の実際の場所に限定されており、仮想空間と現実の場・そこに関わる人々との直接的なリンクを確立している。
チャンは、身近に入手できる素材や電子部品を活用し、ウェブ体験をオープンソース化し、自らの彫刻をつくるための手順を共有することで、アクセス可能なインフラを構築している。彼は従来、個人主義的で孤立しがちだったテクノロジーとの関わりを、共同探求という共有的な試みに再構築している
協力:NEWINC、三菱地所
スペンサー・チャン/Spencer Chang (NEW INC)
スペンサー・チャン
アーティスト、エンジニア、トイ・メーカー。
私たちとテクノロジーの関係性とそれを通して生まれる遊び、創造、そしてケアに関心を寄せている。インターネット空間、インタラクティブな彫刻、そしてクリエイティブツールといった様々なメディアを横断しながら、日常的な実践を通してオンライン上のアイデンティティを探求し、公共の利益となるテクノロジーデザインに取り組んでいる。作品は遊び心と親密さを活用して私たちのシステムに問いを投げかけ、また新たな想像力を掻き立て、それらを再構築するための手段を提示している。
チャンの作品は、Hyundai Artlab(ソウル)、Gray Area & de Young Museum(サンフランシスコ)、Museum of the Moving Image(ニューヨーク)、そしてAlserkal Avenue(ドバイ)などで展示され、プロジェクトは、MIT Technology Review、It's Nice That、そしてFriezeなどのメディアで紹介され、サンフランシスコ芸術委員会とイーサリアム財団からの支援を受けている。New Museumのインキュベーションプログラム「NEW INC」の第11期メンバーであるチャンは、School for Poetic Computation、スタンフォード大学、アジア美術館などでワークショップも開催。
Spencer Chang is an artist, engineer, and toy maker interested in the play, creation, and care that emerges from our relationships with and through technology. Working across internet spaces, interactive sculpture, and creative tools, they engage with everyday practices to explore our online identities and design public good technology. These works leverage whimsical intimacy to interrogate our systems, invite new imaginations, and provide the means to reinvent them.
Chang's work has been showcased by Hyundai Artlab (Seoul), Gray Area & the de Young Museum (San Francisco), Museum of the Moving Image (New York), and Alserkal Avenue (Dubai). Their projects have been featured in MIT Technology Review, It's Nice That, and Frieze, and supported by the San Francisco Arts Commission and the Ethereum Foundation. A NEW INC (New Museum) Y11 member, they have taught and led workshops internationally for institutions such as the School for Poetic Computation, Stanford University, and the Asian Art Museum.
MORE WORKS
ARCHIVE
過去の展示作品を アーカイブとして まとめています。
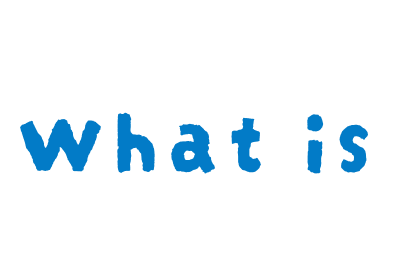
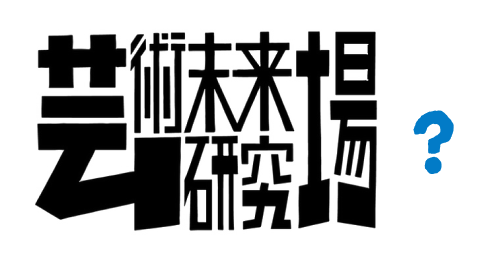
芸術未来研究場は、人が生きる力であるアートを根幹に据え、人類と地球のあるべき姿を探求するための組織として2023年4月に創設されました。閉じた施設としての「研究所」ではなく、様々なプレイヤーが集い、つながり、社会に開かれたアートを実践し、未来を共につくっていく場だから「研究場」と名付けています。
東京藝術大学は、伝統の継承と新しい表現の創造のための教育研究機関であると同時に、アートの未来を常に考え、様々なステークホルダーと共に社会を形づくる主体でもあります。アートの礎である「いまここにないものをイメージする力」は、世界を変え、未来をつくる力です。これまでにも、学部、学科、研究室単位では様々な学外の組織との協働がありましたが、今後は全学横断的にこれを推進していくことで、企業・官公庁・他の教育研究機関との連携を強化し、社会の様々な領域におけるアートの新たな価値や役割を増やしていきます。
また、こうした連携を実践する基盤として、芸術未来研究場では次の6つの領域を設定しました。
 [ケア・コミュニケーション]
[ケア・コミュニケーション]
医療、福祉や地域コミュニティをはじめとするWell-beingな社会づくりにおけるアートの社会的価値を探求します。
 [アートDX]
[アートDX]
デジタル技術やICT技術を活用した教育研究を推進し、アートの可能性を拡げます。
 [クリエイティヴアーカイヴ]
[クリエイティヴアーカイヴ]
多様化する表現手法に対応した、アートの保存・継承と、新たな創造への活用に関する研究を推進します。
 [キュレーション]
[キュレーション]
対話と協働を通してアートと現代社会との関係性を紡ぎ上げる人材の育成と実践研究を行います。
 [芸術教育・リベラルアーツ]
[芸術教育・リベラルアーツ]
東京藝大における教育のあり方を探究しながら、より幅広い対象に芸術教育を拡げ、地域や年齢、社会的属性に関係なく、誰もが自身の人生の中にアートを感じられる社会づくりを推進します。
 [アート×ビジネス]
[アート×ビジネス]
教育研究成果の社会実装・事業化を推進し、芸術産業の創出・発展に寄与します。
これらが互いに領域の枠を超えて混じり合い、芸術と社会の未来を切り拓く新たなプラットフォーム「芸術未来研究場」が、今ここからはじまります。